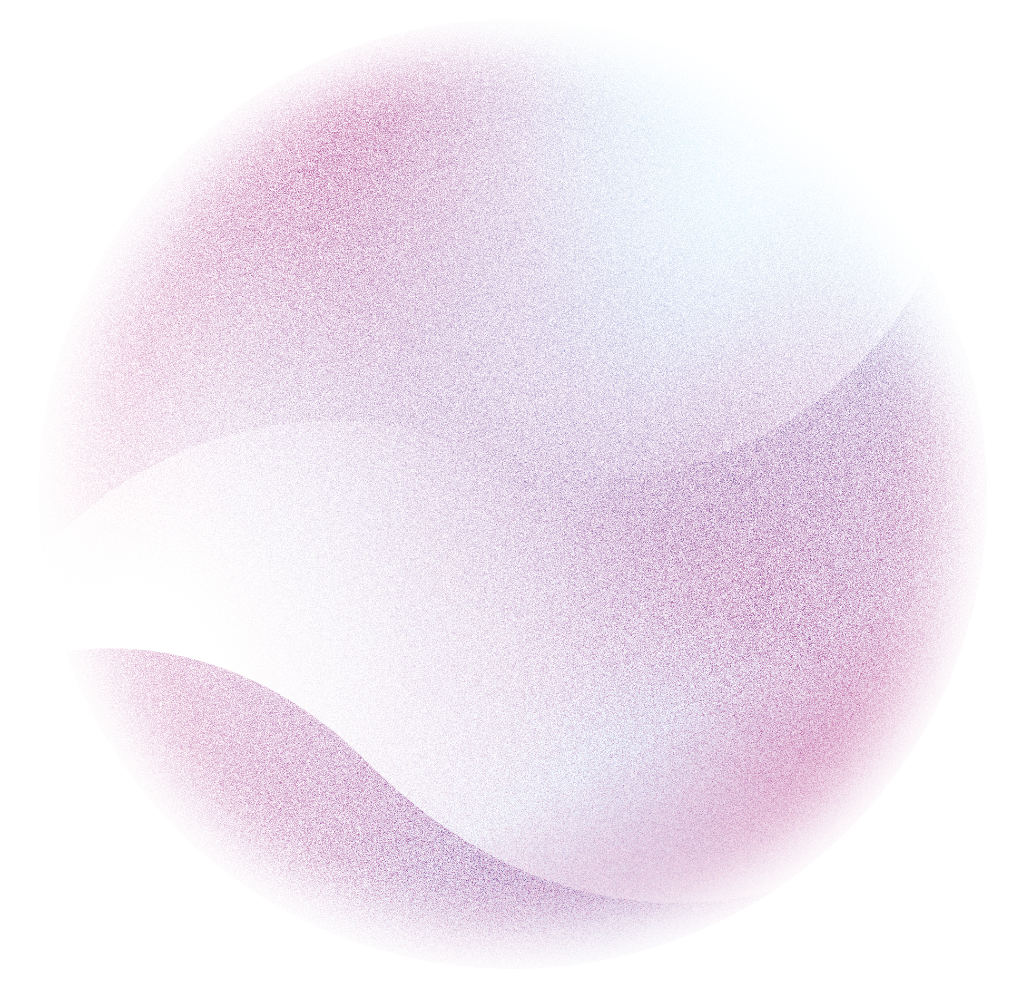
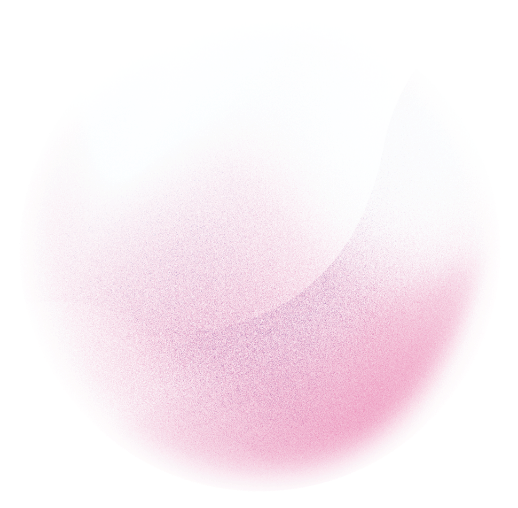
2025.07.22 転職エージェント
ダイレクトソーシングとは?今注目の採用手法を徹底解説

売り手市場が続くなか、従来の「待ちの採用」では優秀な人材の確保が困難になっています。そこで注目を集めているのが、企業から候補者に直接アプローチする「ダイレクトソーシング」という新たな採用手法です。
本記事では、ダイレクトソーシングの基本的な仕組みから導入のステップ、成功事例まで包括的に解説します。従来の採用手法の課題を解決し、自社にマッチした優秀な人材を効率的に獲得するための知識を身につけましょう。
ダイレクトソーシングとは?定義と仕組みを解説

最初にダイレクトソーシングの概要や仕組みなどについて解説します。
(1)基本的な定義と仕組み
ダイレクトソーシングとは、企業の採用担当者が自ら人材データベースなどを活用して候補者を検索し、直接スカウトを行う採用手法です。
求人広告や人材紹介といった「待ちの採用」とは異なり、企業が主体的に候補者にアプローチする「攻めの採用」として注目されています。
この手法では、ダイレクトソーシング専用のデータベースサービスを利用して候補者のプロフィールや職歴を確認し、自社の要件にマッチする人材を見つけ出してから直接コンタクトを取ります。
候補者側も転職を急いでいない潜在層が多いため、転職市場に出る前に、競合他社よりも早い段階でアプローチできる点が大きな特徴です。
(2)ダイレクトリクルーティングとの違い
「ダイレクトリクルーティング」という言葉を聞いたことのある方のなかには、ダイレクトソーシングとの違いについて疑問を持っている方もいるかもしれません。
実は、ダイレクトリクルーティングとダイレクトソーシングは同じ意味で使われています。
厳密には、ダイレクトソーシングが「人材発掘」の部分を指すのに対し、ダイレクトリクルーティングは「採用プロセス全体」を意味しますが、現在では同義語として扱われることが一般的です。
(3)ダイレクトソーシングが注目される背景
ダイレクトソーシングが注目されている背景には、売り手市場と採用ニーズの多様化があります。
少子高齢化に伴う現役世代の減少や有効求人倍率の上昇などにより、求人広告や人材紹介といった既存の採用手法では、人材確保が難しくなっています。
特に、ITエンジニアなどの技術職といった専門性の高い人材は競争が激しく、求める人材に直接アプローチできる採用手法として、注目を集めています。
また採用ニーズの多様化に伴い、ニッチな経験・スキルを持つ人材を求める企業が増えています。しかし希少性の高い人材は、転職サイトや人材紹介サービスで広く募集しても集まらないケースが少なくありません。そうした人材に効率的にアプローチする方法のひとつがダイレクトソーシングです。
採用活動をコントロールしやすい!ダイレクトソーシングの主なメリットとは

ダイレクトソーシングには、従来の採用手法にはないメリットが多数あります。主なものを紹介します。
(1)採用活動をコントロールしやすい
ダイレクトソーシングの最大のメリットは、採用活動をコントロールしやすい点です。企業側から能動的に働きかける採用手法のため、必要なタイミングで必要な人材にアプローチでき、事業の状況に合わせて柔軟に人材を確保できます。
人材紹介会社や転職サイトでの採用の場合、マッチしない人材から応募が集まるケースもあります。ダイレクトソーシングであれば、狙った人材にピンポイントでアプローチできるでしょう。
(2)コストをおさえられる
人材紹介の多くは成功報酬制で、入社した人材の年収の25~35%を手数料として支払います。ダイレクトソーシングの場合は成功報酬制ではなく、採用にかかるコストを削減できます。
特に採用人数が多い場合、人材紹介は人数分の手数料がかかるため、ダイレクトソーシングを利用した方が、1人当たりのコストが大きく下がります。
ただし、成功報酬制のダイレクトソーシングサービスもあるので、事前に確認しましょう。
(3)他媒体では出会えない人材にアプローチできる
他の媒体では出会えない層へのアプローチが可能な点も重要なメリットです。特に専門性の高い職種や経験豊富な管理職層など、一般的な求人媒体に登録していない優秀な人材にもリーチできるため、競合他社が発見できない人材の獲得につながります。
その他にも、「現在は転職を考えていないが、将来的には興味がある」という候補者と継続的な関係をつくれる、アプローチをすることで自社をアピールできるといったメリットがあります。
(4)採用ノウハウを蓄積できる
メールの返信率や内定辞退率などのデータを集めてPDCAを回すことで、採用ノウハウを蓄積できます。自社独自のノウハウを活用すれば、採用成功の再現性が高まり、より採用活動をコントロールしやすくなります。
人材紹介会社などに採用を丸投げしていると、採用ノウハウが蓄積されず、長期的な採用戦略に悪影響が及ぶかもしれません。
運用の負担が増える?ダイレクトソーシングのデメリットと対策とは

採用活動をコントロールできるなどメリットの多いダイレクトソーシングですが、いくつかデメリットがあります。対策も合わせて紹介します。
(1)運用工数が増える
最も大きな課題は運用工数の増加です。候補者の検索、スカウトメールの作成・送信、返信対応、面談の調整などをすべて自社で実施しなければいけません。企業側が積極的にアプローチするという性質上、人材紹介や転職サイトを利用した採用活動などよりも、業務量は増える傾向にあります。
また採用の可能性を高めるため、候補者からの返信があった場合、温度が冷めないうちに迅速にレスポンスし、面談をセットアップする必要があります。
効率的な運用体制の構築や、必要に応じて外部サービスの活用を検討することが重要です。
(2)採用が難しい場合もある
求める人材によっては、希望する人材を見つけられない可能性があります。
検索してもヒットする候補者が少ない、アプローチしても返信が来ないという場合は、条件をゆるめるのも方法のひとつです。
現場部門とすり合わせをして、本当に必要な条件を洗い出し、ある程度条件にあてはまる人材には積極的にアプローチしましょう。
現場とスムーズにすり合わせを行えるよう、採用担当者が現場の業務についての知見を身につけるのも重要です。
また、ダイレクトソーシングサービスによって登録者の年齢層、職種、スキルレベルが異なるため、ターゲットとする人材が多く登録されているプラットフォームを選ぶことが重要です。
複数のダイレクトソーシングサービスを利用することで、より幅広い候補者にアプローチできます。
(3)スカウトメールの返信が来ない
魅力的な人材は競争率が高く、スカウトメールを送っても返信が来ないケースもあります。
そこで重要なのが、スカウトメールの作成です。候補者のどの部分に魅力を感じているかを具体的に伝え、自社での活躍イメージを明確に示して熱意をアピールしましょう。求職者にとってのメリットや成長機会を具体的に提示することで、返信率の向上が期待できます。
また会社の認知度が低い場合、スカウトメールの返信率に影響が出る可能性があります。
社員紹介ページの充実、企業文化の発信、オウンドメディアの構築など、認知度向上に向けた施策を並行して実施することが効果的です。
まとめ

ダイレクトソーシングは、企業が優秀な人材に直接アプローチできる「攻めの採用」として注目を集めています。
採用活動を柔軟にコントロールでき、コスト削減や他媒体では出会えない人材との接点が得られるなど、多くのメリットがあります。
一方で、運用の手間や返信率の低さといった課題もあるため、成功には効率的な体制構築や的確なプラットフォームの選定、候補者に響くスカウトメールの工夫が不可欠です。
自社に合った運用スタイルを確立できれば、ダイレクトソーシングは他社と差別化できる強力な採用戦略となるでしょう。
不安がある場合は、人材紹介や求人広告と併用しながら、段階的に導入を進めていくことも検討してみてください。





