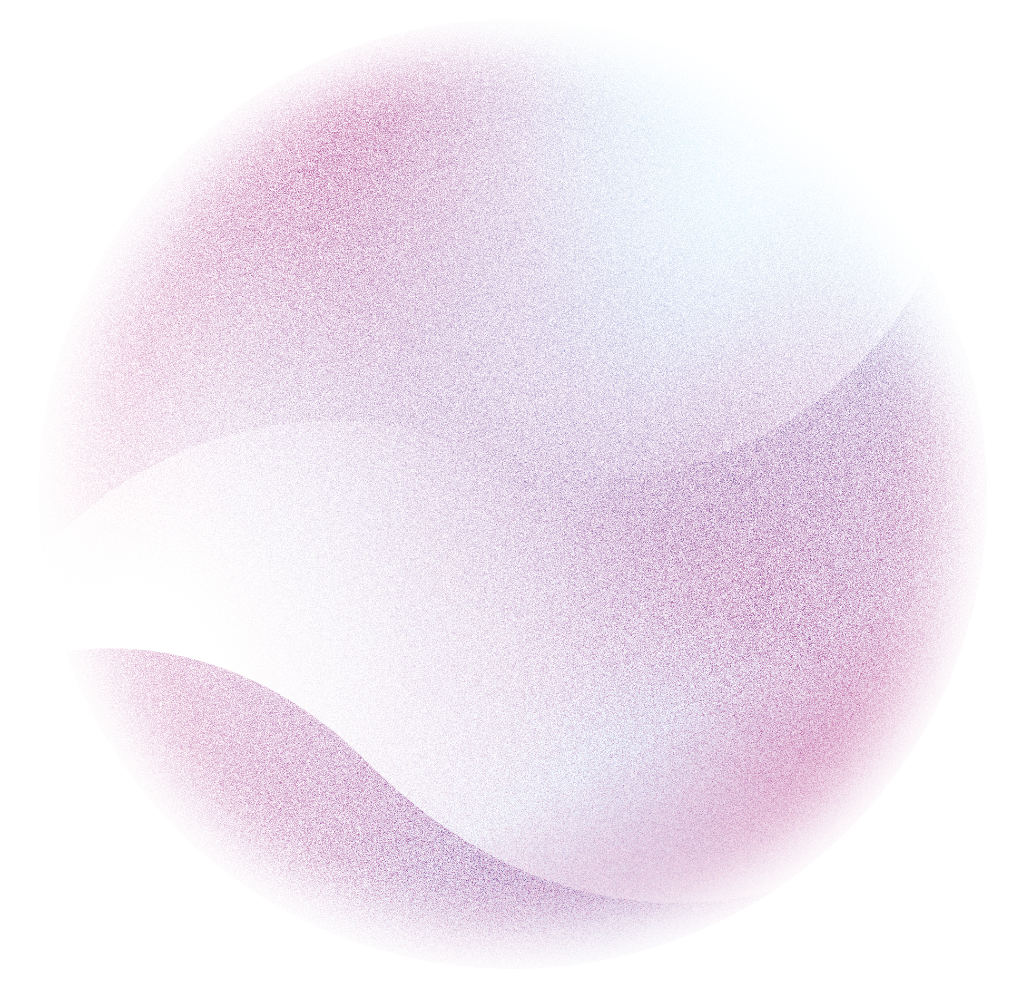
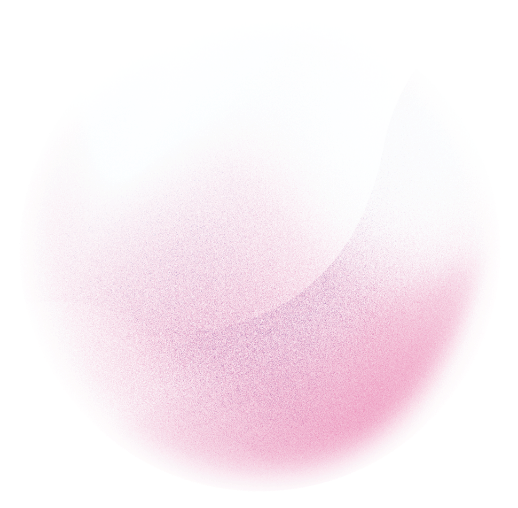
2025.08.26 転職エージェント
採用が難しい場合はどうする?課題や対応策を解説

少子高齢化や専門性の高度化などを背景に、採用市場の競争は年々激化しています。優秀な人材の確保は、企業にとって重要な課題です。
特に専門性の高い職種や人材ニーズの高い業界は、採用が難しいケースが多く、頭を悩ませている採用担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、採用が難しい職種の特徴と対策、効果的な採用戦略、採用部門を強化する方法について解説します。
採用が難しいのはなぜ?主な理由を紹介

現代は多くの企業が、採用難に直面しています。主な理由を紹介します。
(1)転職市場の変化
少子高齢化が進むなか、現役世代の数は減り続けています。そのため、若手人材を中心に売り手市場が続いており、採用競争が激化しています。
今後、少子高齢化はさらに深刻化すると見込まれ、採用難も継続するでしょう。
(2)仕事への価値観の変化
若手人材を中心に、ワークライフバランスを重視する・転職や独立を視野に入れて入社するといったような、仕事への価値観の変化が見られます。
長期間労働や低賃金など労働環境に不満があると、離職を選ぶケースが多く、人手不足の原因のひとつになっています。
(3)専門性の高度化
デジタル化の推進に伴い、多くの職種で求められるスキルが高度化しています。
特にIT関連職種では専門性の高い人材の確保が非常に困難です。これは技術の進歩スピードが速く、知識・経験のアップデートが必要な職種が増加していることが背景です。
採用が難しい職種でも成果は出せる!課題と対策を紹介

採用が難しい理由と対策は、職種によって異なります。特に採用難易度の高い4職種について、課題と対策を紹介します。
(1)建築・土木技術職
建築・土木技術職は、長年にわたり人手不足が続く、採用難易度の高い職種です。特に2024年には働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限を遵守しなければならなくなりました。
これまで長時間労働が常態化していた建築・土木業界において、時間外労働の制限により従来の働き方が困難になり、より多くの技術者が必要になっています。
重労働・危険・上下関係が厳しいといったイメージが強く、負担が大きいわりに待遇が低いということから、若手人材の業界離れが進んでいるのが現状です。さらに、ベテランの高齢化と退職により、現場の技術継承が滞っています。
主な対策は、未経験の若手を対象とした教育制度の整備・労働環境の改善・明確なキャリアパスの提示です。
また、人間関係の良さや最先端の技術の活用といった、職場の魅力をSNSなどで積極的に発信するのも効果的です。
(2)ITエンジニア
IT業界では技術革新のスピードが速く、常に最新の技術に対応できる人材が求められています。しかし、そうした人材は非常に限られており、企業間での獲得競争が激化しています。特にAIやクラウド技術、セキュリティ分野の専門家は、非常にニーズが高く、採用難なのが現状です。
採用成功のためには、資格取得支援制度・技術カンファレンスへの参加支援・社内勉強会といった、エンジニアのスキルアップをバックアップする体制を整える必要があります。
さらに、技術的な挑戦ができるプロジェクトの存在や、裁量の大きな働き方、リモートワークなど柔軟な勤務スタイルも重要なアピールポイントになります。
(3)医療・介護職
医療・介護職の採用が難しい主な原因は、高齢化社会によるニーズ増と労働環境の厳しさです。夜勤や休日勤務などの不規則な勤務形態、精神的・肉体的負担の大きさなどが求職者にとって大きなハードルとなっています。
さらに、専門資格が必要で参入障壁が高い一方、他業界と比較して給与水準が低いことも人材確保を困難にしています。
最も重要なのは、ワークライフバランスの改善です。柔軟な勤務シフト・休暇取得率の向上・職場環境の整備により働きやすい環境を整える必要があります。
また、継続的なスキルアップ支援や専門資格取得の補助制度、明確なキャリアパスの提示により、専門職としての成長機会を提供することも重要です。
さらに、人材の裾野を広げる取り組みも効果的です。具体的には、看護師免許を持ちながら看護の仕事をしていない潜在看護師や介護士の復職支援プログラムの充実、未経験者向けの教育制度の整備などがあげられます。
(4)営業職
営業職の従来のイメージと現代の働き方の価値観はギャップが大きく、採用の難しさにつながっています。営業職は成果主義の傾向が強く、ノルマが厳しい・残業が多い・顧客対応のストレスが大きいといった状態になりやすい点が、若手人材から敬遠されがちです。
また営業職はどの企業でも必要とされており、競合が多い点も、難易度を上げています。
対策としては、営業の役割とキャリアパスを再定義し、ネガティブなイメージを払拭することが大切です。単なる商品販売ではなく、顧客の課題解決を支援するコンサルタントとしての価値を明確に示しましょう。
また、デジタルツールを活用した効率的な営業活動の導入、適切な目標設定とサポート体制の整備により、働きやすい環境を構築することが重要です。さらに、高水準の基本給と成果報酬のバランスが取れた給与体系を整え、収入の安定性を確保するのも効果的です。
採用が難しいと感じる担当者へ!効果的な採用戦略4選

現在は採用難易度が高く、これまで通りの方法では人材を獲得できない場合が少なくありません。おすすめの採用戦略を紹介します。
(1)採用ブランディングの強化
採用ブランディングとは、自社の魅力や価値を整理し、求職者に伝えるためのコミュニケーション全般を指します。コーポレートサイト・SNS・求人広告などさまざまな場で、一貫したメッセージとして発信することが重要です。
成長志向の強い人材が欲しい場合は学習機会や挑戦的なプロジェクトをアピールするなど、ターゲットに応じたメッセージを発信すると効果的です。
また、実際に働く社員の声や具体的な成功事例を交えることで、メッセージの信頼性と訴求力を高められます。
(2)条件面の改善
自社の給与水準と求職者の希望年収がマッチせず、採用成功に至らないケースは少なくありません。条件面での競争力は、採用成功の重要な要素です。
しかし、単純な給与の引き上げだけでは不十分です。フレックス制度などの柔軟な勤務スタイル・充実した研修制度・明確な評価制度・手厚い福利厚生など、金銭面以外の価値も含めた待遇改善が必要です。
特に若手人材に対しては、成長機会や学習支援制度の充実が、給与以上に重要な決定要因となることが多いため、環境を整えるとともに、適切にアピールしましょう。
(3)データ活用による改善
採用活動の効果を客観的に評価し、継続的に改善するためには、データの活用が重要です。応募数・面接通過率・内定承諾率・早期離職率など、各段階での数値を継続的に追跡し、課題を洗い出すことで、より効果的な採用戦略を立てられます。
特に重要なのは、採用コストと採用の質のバランスの分析です。どの採用チャネルが最も費用対効果が良いか、どのような候補者が長期的に活躍しているのかなど、定量的な分析に基づいた意思決定を行うことが重要です。
(4)多様な採用チャネルの活用
従来の求人媒体だけでなく、SNSや専門コミュニティ、リファラル採用(社員からの紹介)など、多様なチャネルを組み合わせることで、より多くの候補者にアプローチできます。
特にSNSを活用した採用活動は、企業の日常的な活動や社員の生の声を伝えることで、求職者との距離を縮める効果があります。
また、業界特化型の転職サイトや転職エージェントの活用も効果的です。特定分野に精通したキャリアアドバイザーが在籍しており、自社のニーズに適した候補者を紹介してもらえる可能性が高いでしょう。
まとめ

採用難の背景には、少子高齢化による人材不足・働き方に対する価値観の変化、専門性の高度化などがあります。
特に建築・土木技術職、IT業界、医療・介護職、営業職では、それぞれ特有の課題があるため、職種別の対策が必要です。
効果的な採用戦略として、採用ブランディングの強化・条件面の改善・データ活用による継続的な改善・多様な採用チャネルの活用があげられます。





