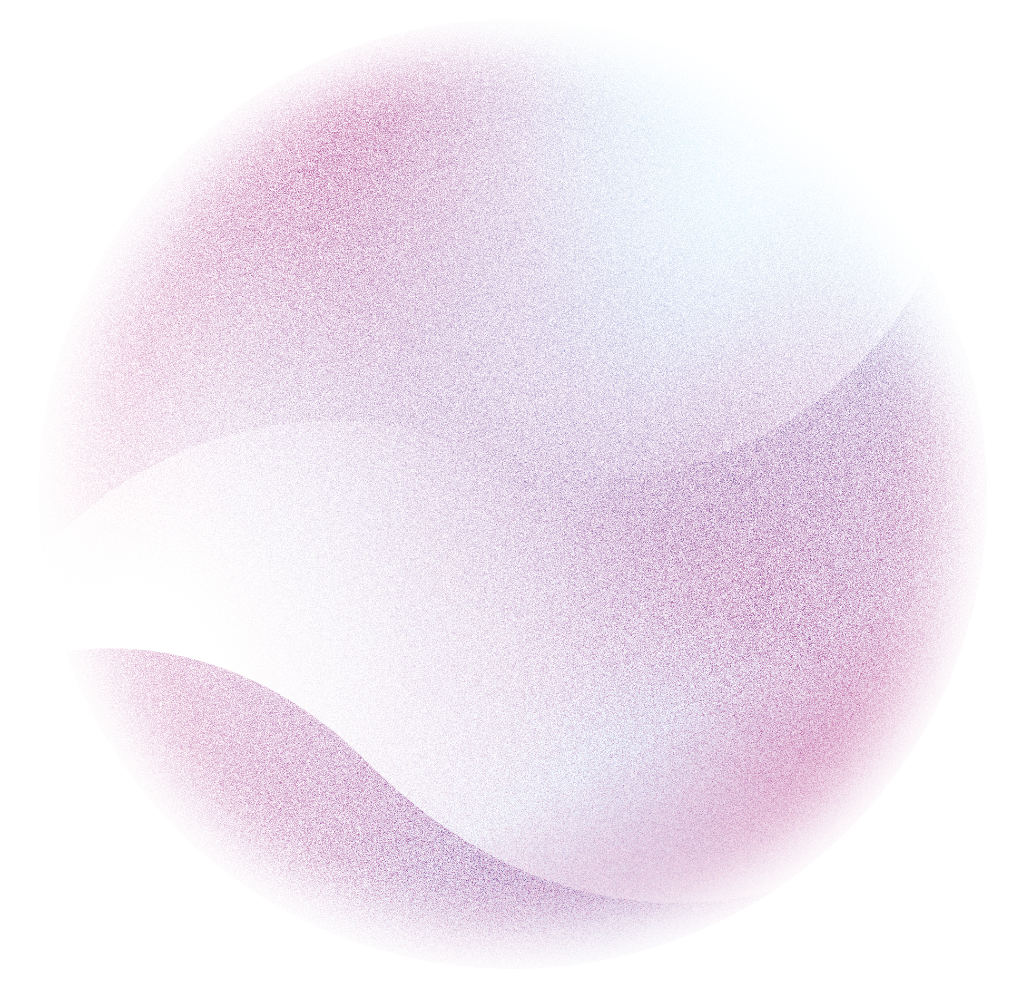
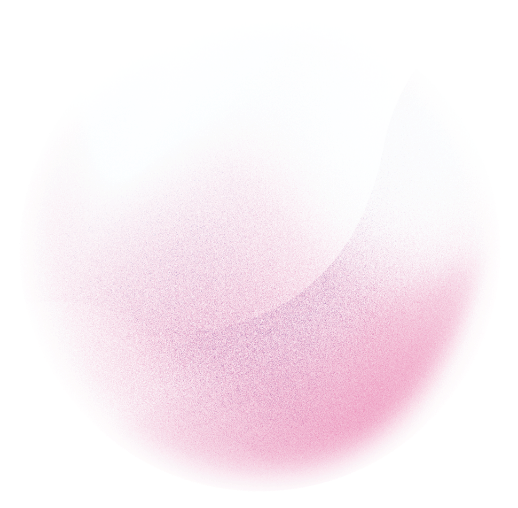
2025.10.15 採用
採用担当者は必見!リファレンスチェックの内容や質問項目などを解説

リファレンスチェックは、応募者の人柄や仕事ぶりを深く理解し、ミスマッチを防ぐ重要なプロセスです。近年中途採用で、リファレンスチェックを実施するケースが増えています。
この記事では、導入を検討している採用担当者向けに、概要、目的や具体的な質問内容、さらに実施時の注意点について詳しく解説します。メリット、具体的なツールの選び方、そして有効活用する方法まで詳しく解説します。
リファレンスチェックってどんなもの?概要や目的について解説

最初にリファレンスチェックの概要や目的を解説します。
(1)リファレンスチェックの概要
リファレンスチェックは、応募者の人柄や仕事ぶりを確認するために、企業が関係者にヒアリングする調査です。
応募者が提出した履歴書や職務経歴書、そして面接で自己申告した内容が、事実に基づいているか、また実態とかけはなれている点がないかを検証するために実施されます。リファレンスチェック結果は、採用の最終的な判断材料として活用します。
リファレンス先は、主に応募者の過去の勤務先における直属の上司、同僚、または人事担当者などの第三者です。
(2)リファレンスチェックの目的
最大の目的は、採用の精度を高め、入社後のミスマッチや重大なトラブルを防止することです。
応募書類と面接という限られたやり取りでは、応募者の潜在的な強みや弱み、職場での実際の振る舞いを完全に把握することは困難です。
リファレンスチェックをすることで提出書類や面接の回答といった情報を裏付け、経歴詐称などのリスクを軽減できます。
応募者の自己評価と他者評価のギャップを埋められるのも大きなメリットです。関係者に客観的な評価を聞くことで、応募者が持つスキルや経験が、募集ポジションで実際に通用するか、企業の文化やチームに適応できるかを見極めやすくなります。
また、応募者の仕事への姿勢や行動特性は、採用後の定着支援やパーソナライズした人材育成に活かせる貴重な情報です。活用することで、早期戦力化と定着率向上につながります。
リファレンスチェックで確認すべき内容とは?具体的な質問項目を紹介

リファレンスチェックで確認する内容は、大きく「経歴に関する事実関係」「人柄や行動特性」「業務遂行能力」の3種類に分類されます。
それぞれの概要と具体的な質問項目は、以下の通りです。
(1)経歴に関する事実関係
履歴書などに記載された基本的な情報の正確性を担保する質問です。在籍期間や役職、所属部署、勤務状況などについて確認します。
<質問例>
・応募者の在籍期間、役職、所属部署について教えてください。
・応募者との関係性や一緒に働いた期間をお聞かせください。
・応募者の休暇取得、残業時間などの状況はいかがでしたか?
(2)人柄や行動特性
自社の社風やチームに適合するか、組織の一員として適切に振る舞えるかを見極めるための質問です。コミュニケーション能力、チームワーク、リーダーシップ、ストレス耐性などについて確認します。
スキルが高くても文化に合わなければ早期離職のリスクが高まるため、定着率と入社後の活躍度を高める上で重要な質問です。
<質問例>
・あなたと応募者はどのような関係性でしたか?
・周囲とのコミュニケーションの取り方はどのようなものでしたか?
・応募者とまた一緒に働きたいですか?
・応募者を周囲に紹介するとしたら、どのような言葉で表現しますか?
・応募者はメンバー間で意見が対立した時、どのように対処していましたか?
(3)業務遂行能力
前職でどのような成果を上げ、どのようなスキルを発揮していたかを把握するための質問です。具体的な実績、課題解決能力、専門知識の深さなどを確認し、実績を実務でどのように実現したかを客観的に把握できます。
<質問例>
・応募者の最も大きな実績は何でしたか?それはどのような状況で、どのように達成されましたか?
・応募者の強みは何ですか?
・応募者が改善すべき点があるとすると、どんな点ですか?
休職歴・健康状態・家族構成など、採用に直接関わらない情報や機密性の高い情報を尋ねることは避けましょう。
リファレンスチェックはどう進めるの?一般的な流れを紹介

リファレンスチェックの一般的な流れは、以下の通りです。
【1】応募者から事前に同意を得る
【2】リファレンス先の選定依頼
【3】リファレンス先への連絡・日程調整
【4】質問項目の設計などの準備
【5】リファレンスチェックの実施
【6】結果・評価のまとめ
各項目について、一つずつご紹介いたします。
【1】応募者から事前に同意を得る
本人の同意なしに個人情報を第三者から取得すると、個人情報保護法違反となる可能性があります。応募者に実施する旨を説明し、書面などで必ず事前に同意を得てください。
【2】リファレンス先の選定依頼
応募者に、必要な人数やどんな人物を希望するか伝え、リファレンス先の選定を依頼します。複数候補を出してもらい、自社で誰に依頼するか指定します。
【3】リファレンス先への連絡・日程調整
先方に連絡を取り、協力の依頼や日程調整をします。実施まで時間が空くと応募者が他社への転職を決めてしまうリスクがあるので、できるだけ早めの日程を設定しましょう。
【4】質問項目の設計などの準備
必要な情報をスムーズにヒアリングできるよう、事前に採用担当者が質問項目を検討します。事前に質問内容を共有するケースもあります。
【5】リファレンスチェックの実施
メール・オンライン・電話などで実施します。オンラインや電話の場合、話し方や微妙なニュアンスも重要な情報なので、見逃さないようにしましょう。また、リファレンス先は厚意で協力してくれています。感謝を伝え、ヒアリング時間を最小限にするなど負担を抑える配慮が必要です。
【6】結果・評価のまとめ
収集した情報は社内で共有し、面接の情報と照らし合わせて、総合的に評価します。
リファレンスチェックで注意するポイントって?代表的な4つを紹介

リファレンスチェックをスムーズに実施し、トラブルを防ぐために、以下のようなポイントに注意しましょう。
(1)必要性を検討する
リファレンスチェックの実施には、時間や人的リソースがかかります。また、応募者がリファレンス先を探す手間もかかるため、やみくもに実施するのは避けましょう。
一定以上のポジションの選考に限り行うなど、あらかじめ基準を定め、本当に必要な場合のみ行うのをおすすめします。
(2)完了した旨を応募者に伝える
リファレンスチェックが完了したら、すみやかに応募者に完了した旨を伝えましょう。安心感につながりますし、応募者が「リファレンス先にお礼を言いたい」と考えているかもしれないからです。
(3)リファレンスチェックの内容だけで不採用を決めない
リファレンスチェックの回答は、あくまでリファレンス先から見た一意見です。ネガティブな情報があったとしても、それだけで不採用にするのは避けましょう。
面接や他のリファレンス先へのヒアリングを通して事実確認するなど、さまざまな角度から検討することが、公正な採用活動につながります。
(4)不採用を伝える際は細心の注意を払う
リファレンスチェック後に不採用を伝える際は、応募者が「リファレンスチェックが原因で不採用になった」と疑念を抱かないよう、伝え方に配慮しましょう。
不用意な伝え方をすると、応募者とリファレンス先の関係が悪化するリスクがあります。
まとめ

リファレンスチェックは、元上司や元同僚などの第三者からヒアリングし、応募者の客観的な情報を収集する調査のことです。ミスマッチを最小限に抑え、採用の精度を高めることを目的としています。
確認すべき内容は、経歴の事実関係、人柄や行動特性、そして業務遂行能力の3種類です。
実施にあたっては、応募者の同意を必ず得る、公正な判断のためにリファレンス情報だけで不採用を決めないといった注意点を守りましょう。 適切に活用することで、採用の質を高め、長期的な組織力の強化につなげられます。





