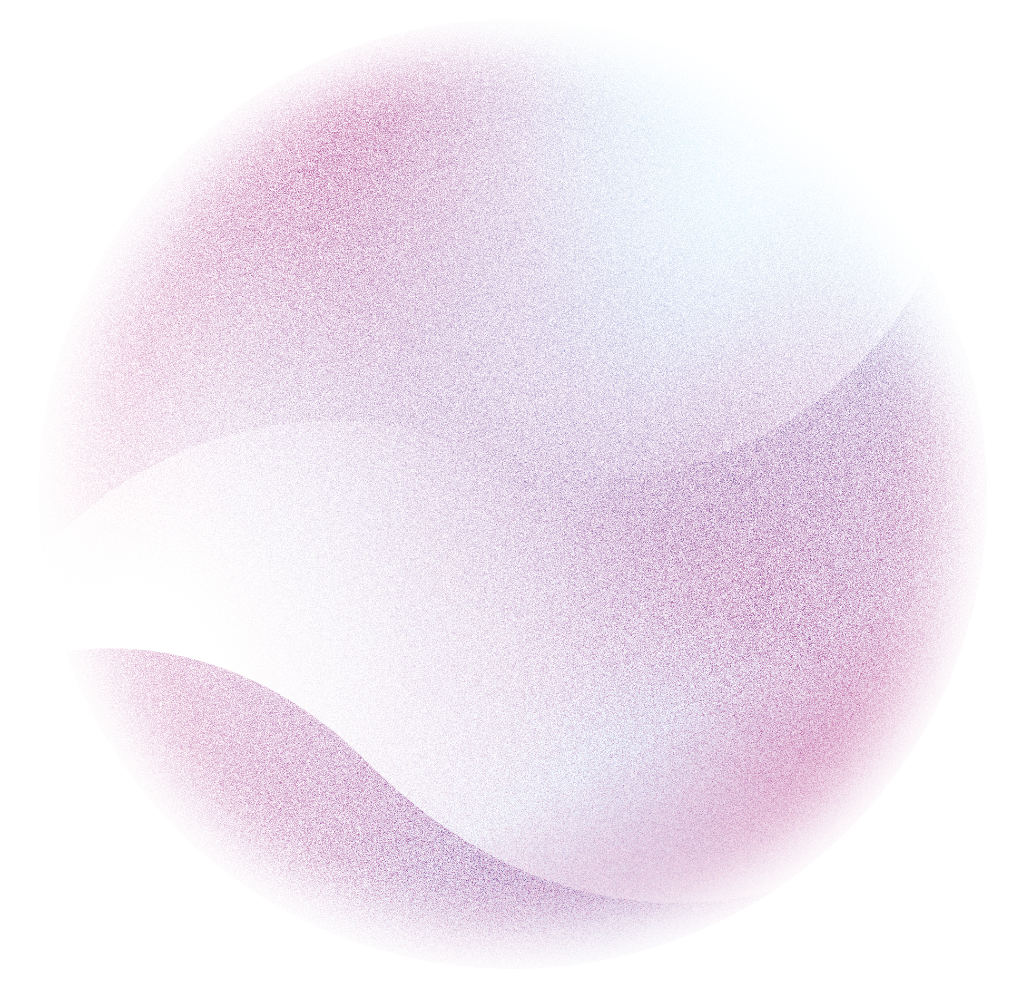
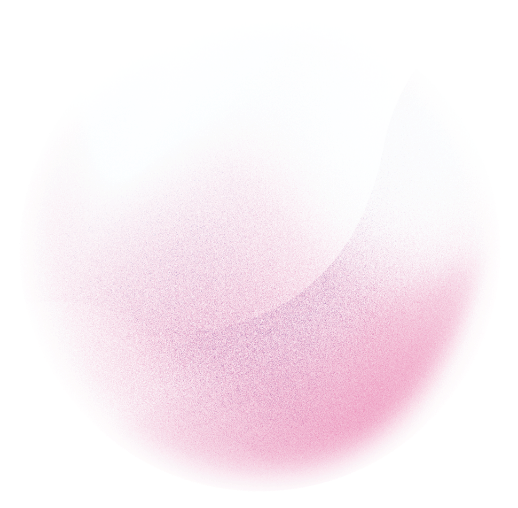
2025.11.15 採用
採用の質を高める!非構造化面接のメリットと導入時の注意点

非構造化面接とは、会話の流れに沿って自由に応募者と対話する面接手法です。応募者の潜在的な能力や人柄を深く理解できるため、近年注目されています。
非構造化面接に興味はあるものの「どんな面接方法かよく分からない」「具体的に何を質問すれば良いのか」と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、非構造化面接の概要やメリット、構造化面接との違い、デメリットなどを解説します。さらに、具体的な質問例も紹介します。
非構造化面接とは?メリットや構造化面接との違いを解説

非構造化面接の定義やメリット、対極にある構造化面接との違いを解説します。
(1)非構造化面接とは
非構造化面接とは、面接の具体的な質問内容や順序、評価基準を事前に詳細に定めず、応募者との対話の流れに応じて柔軟に進める面接手法のことです。
面接官の裁量が大きく、応募者の発言内容や態度に応じて質問を掘り下げ、多角的な情報を引き出すことを目的としています。
(2)非構造化面接のメリット
非構造化面接の大きなメリットは、面接官が自由に質問できるため、応募者の隠れた一面や思考の柔軟性、価値観といった定量化しにくい部分を引き出しやすい点です。
画一的な評価では見逃されがちな、その人ならではの強みやポテンシャルを発見しやすいため、特に創造性や柔軟性が求められる職種の採用に効果的です。
その他、質問内容を決めていない分コミュニケーションを深めやすく自社の魅力をアピールできる、自社の採用方針の変更にも容易に対応できるといったメリットもあります。
(3)構造化面接との違い
構造化面接とは、面接の具体的な質問内容や順序、評価基準を事前に決め、全ての応募者に対して同じ手順で面接を実施する手法です。
構造化面接は、評価のバラつきをおさえ、合否の理由を客観的に説明しやすいというメリットがあります。
その一方、質問項目や評価基準を決める手間がかかる、質問の自由度が低いため応募者のパーソナルな部分を深掘りするのが難しいといったデメリットもあります。
採用の目的やフェーズに応じて、公平性を重視する一次面接では構造化面接、人柄やカルチャーフィットを重視する最終面接では非構造化面接といったように、両者を組み合わせるのも方法のひとつです。
また、事前に用意した質問をしつつ、面接官の裁量で応募者の返答を深掘りする質問もする半構造化面接という手法もあります。
客観的な評価が難しい?非構造化面接のデメリットとは

応募者の意外な一面を発見できるなどメリットの大きい非構造化面接ですが、気をつけるべきデメリットもあります。
(1)評価の客観性を保ちにくい
非構造化面接の最大のデメリットは、質問や評価基準の自由度が高い分、面接官の主観やバイアスが入りやすいことです。
バイアスとは、判断や意思決定などに影響を与える思考の偏りや先入観のことです。代表的なものに、第一印象で相手のことを決めつけて裏付ける情報を集めてしまう確証バイアス、自分と似た人を高く評価してしまう類似性バイアスなどがあります。
人間は誰しもバイアスを持っていますが、面接の場では特にバイアスが入りやすい傾向にあるので、注意が必要です。バイアスの影響で、マッチしない人材を採用したり、逆に優秀な人材を逃したりする可能性があります。
(2)面接官のスキルへの依存度が高い
非構造化面接を効果的に行うには、応募者の本質を見抜く洞察力や、適切な質問を瞬時に生み出す対話能力が必要不可欠です。
経験やトレーニングが不足している面接官が担当した場合、一般的な質問や自分が関心を持っている事柄ばかり質問してしまい、必要な情報を十分に引き出せないまま面接が終わってしまうリスクがあります。
(3)自社のイメージを損なうリスクがある
自由度が高い分、話の流れで不適切な質問をしたり、スムーズに受け答えができなかったりすることで、自社のイメージを損なうかもしれません。
非構造化面接の効果を最大化するために!おすすめの対策4選

非構造化面接のデメリットを防ぎ、採用成功につなげるには、次のような対策が効果的です。
(1)採用関連の法律・ルールを習得する
非構造化面接では面接官が自由に質問するため、構造化面接よりも質問や説明の際に、コンプライアンス違反を犯すリスクが高まります。
例えば、「結婚後も仕事を続けますか?」といったハラスメントに該当する質問をしてしまうといった事態が考えられます。
採用関連の法律・ルールは、面接をするうえで必須の知識ですが、非構造化面接を実施する場合は、知識・リテラシーをあらためて確認しましょう。
(2)バイアスについて理解する
非構造化面接では、構造化面接よりもバイアスが出やすい傾向にあるので、面接官がバイアスについて理解することが重要です。
バイアスの知識があれば、評価をする時に自分のバイアスに気づき、客観的な基準で評価できるでしょう。
(3)面接の目的を明確にしておく
非構造化面接は面接官の裁量で質問するため、面接の目的があいまいだと、適切な質問ができず、必要な情報を得られないリスクがあります。
求める条件や自社のカルチャーと応募者の経歴を照らし合わせ、「社風とマッチするかを見極める」「チームマネジメント力を知りたい」といったように、面接の目的を明確化することで、聞くべき質問を見極めやすくなります。
(4)ロールプレイングをする
非構造化面接では、応募者の反応から心情・思考・意図を把握し、適切な質問を導き出すスキルが欠かせません。
ロールプレイングを行い、フィードバックをもとに改善するサイクルを繰り返し、臨機応変に効果的な質問を行うスキルを習得しましょう。
非構造化面接を成功させるために!具体的な進め方と質問例

非構造化面接の流れや質問内容について解説します。
(1)非構造化面接の流れ
非構造化面接では、応募者の言葉に耳を傾け、「なぜそう思うのですか?」「その時、具体的にどう行動しましたか?」といった深掘りする質問を投げかけていきます。
この時、はい・いいえで答えられる質問ではなく、「~について教えてください」といったオープンな質問をすることで、応募者の考えや価値観を把握しやすくなります。
また、本音を引き出すために、笑顔で相づちを打つなどリラックスして回答できる雰囲気づくりが大切です。
基本的に質問内容は自由ですが、面接官からの質問で面接がスタートするので、導入時の質問内容はあらかじめ決めておきましょう。
(2)質問例
非構造化面接に適した質問の例を紹介します。
・導入時の質問
「自己紹介をお願いします」「当社を志望した理由は何ですか?」といった定番の質問か、アイスブレイクもかねて応募者の興味に合わせた質問をするとスムーズです。
・価値観を知るための質問
「あなたが仕事をする上で、譲れない価値観は何ですか?それはどのような経験から形成されましたか?」と聞くことで、行動の根源となる価値観が明確になり、自社の理念・カルチャーとの適合性を確認できます。
・行動特性を知るための質問
「あなたのチームで意見が対立した時、どのように解決に導きましたか?」など実際のエピソードを聞くと効果的です。協調性やコミュニケーションスタイルなど、組織での振る舞い方がわかります。
質問への回答を聞いて満足するのではなく、少しでも気になる点があれば「なぜですか?」と深掘りすることで、より充実した面接になります。
まとめ

非構造化面接は、質問や評価基準を事前に詳細に定めず、応募者と臨機応変に対話しながら進める面接手法です。
応募者の人柄や価値観、潜在能力といった定量化しにくい部分を深く理解できるメリットがあり、特に創造性が求められる職種の採用に効果的です。
しかし、面接官の主観やバイアスが入りやすく評価の客観性を保ちにくい、面接官のスキルへの依存度が高いなどのデメリットもあります。
非構造化面接で成果を出すには、面接官が採用関連の法律やバイアスについて正しく理解することが重要です。また、面接の目的を明確にし、ロールプレイングを通じて対話スキルを磨く必要があります。
面接では、応募者の言葉を深掘りするオープンな質問を心がけ、本音や行動特性を引き出すようにしましょう。





