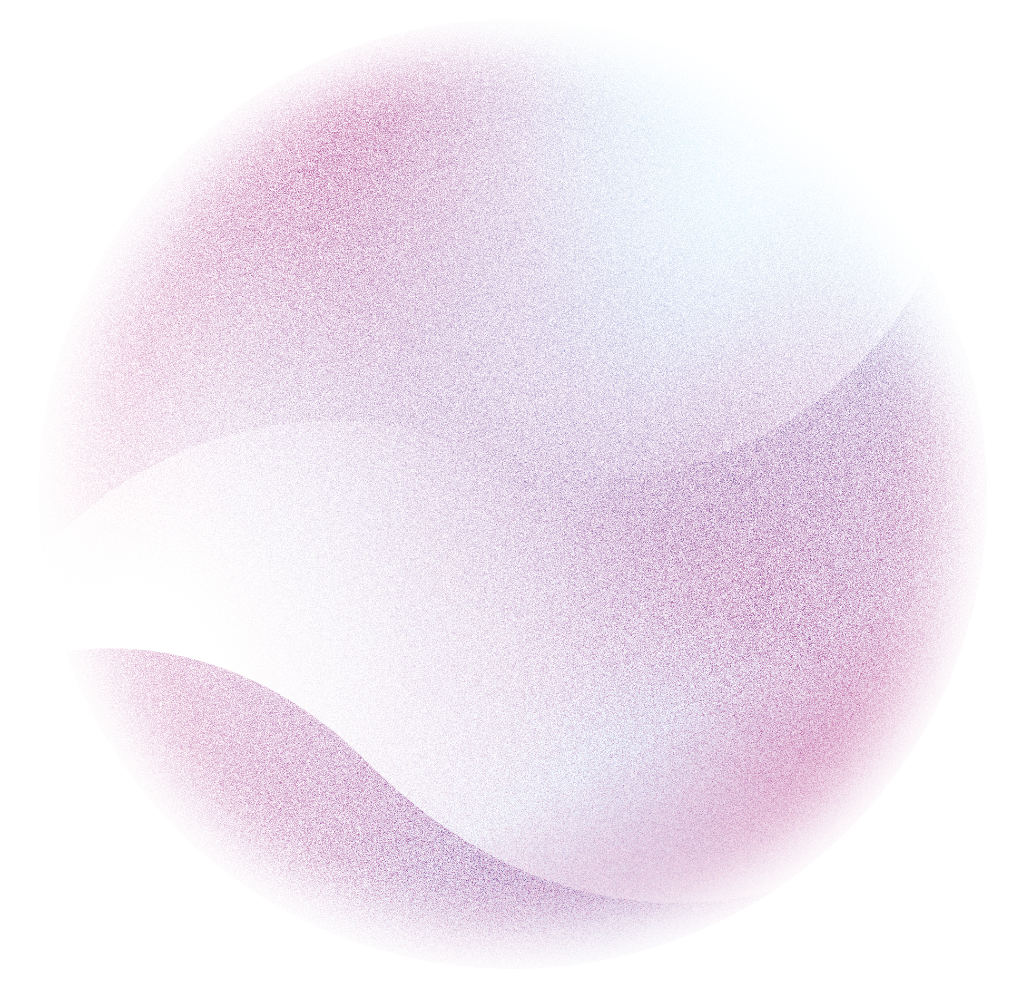
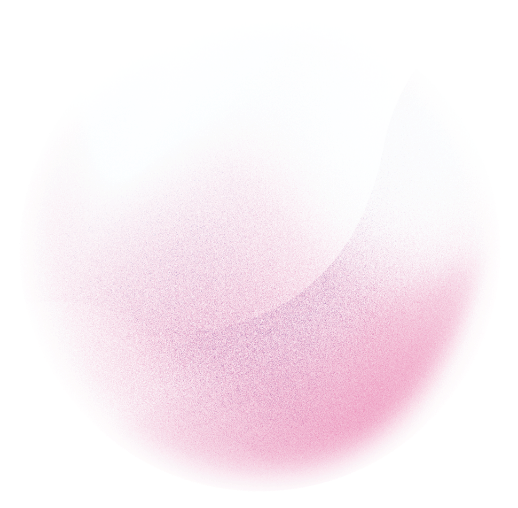
2025.08.26 採用
採用担当あるあるを紹介!代表的な事例と解決法について解説

採用担当者の方なら、「これ、うちだけじゃないよね?」と思ったことがあるのではないでしょうか。
面接のハプニングや応募者対応の悩みなど、採用現場には「あるある」な出来事がつきものです。
面接での思わぬハプニングや、求職者とのやり取りで生じる小さな苦労など、採用現場には共通の悩みやエピソードがたくさんあります。
この記事では、そんな採用担当なら誰もが一度は経験するであろう、あるあるを紹介し、業務効率化や改善につながる具体的な対策をお伝えします。
面接中のあるあるって?代表的なエピソード5選とその対策

面接は応募者と直接話ができる貴重な機会ですが、思わぬ事態が起きる場合も少なくありません。ここでは、面接のあるあるエピソードと対策を紹介します。
(1)面接開始時間になっても応募者が現れない
面接開始時間を15分過ぎても応募者が現れず、慌てて連絡を取った経験がある採用担当者は多いのではないでしょうか。
交通機関の遅延が原因の場合もあれば、単純に時間を間違えていたというケースもあります。こういった事態を避けるためには、面接前日に確認の連絡を入れることが効果的です。面接時間や場所の再確認とともに、緊急連絡先も共有しておくと安心です。
(2)応募者が緊張しすぎて言葉が出てこない
特に新卒採用や転職初心者の面接では、緊張して言葉が出なくなる応募者も珍しくありません。このような場合、採用担当者の対応が応募者の本来の実力を引き出すカギとなります。
まずは「緊張されているようですが、大丈夫ですよ」と声をかけ飲み物を出したり、軽い世間話から始めたりして雰囲気を和らげましょう。
(3)質問に対して的外れな回答が返ってくる
「当社の志望動機を教えてください」という質問に対して、業界全体の話や個人的な体験談を長々と語る応募者もいます。このような状況では、優しく軌道修正を図ることが大切です。
「ありがとうございます。では、数ある会社の中でも特に当社を選んだ理由について教えていただけますか」といった具合に、より具体的な質問に言い換えて誘導しましょう。
(4)面接時間が予定よりも大幅に延びてしまう
話が盛り上がりすぎて予定時間を大幅に超過してしまうケースもあります。面接開始時に「本日は貴重なお時間をいただき、○時頃までを予定しております」と時間の目安を伝えておくと良いでしょう。
また、重要な質問事項をリスト化し、優先順位をつけておくことで、限られた時間の中でも必要な情報を確実に収集できます。
(5)想定外の質問を受けて答えられない
応募者から「この会社の10年後の姿をどう見ていますか」といった逆質問を受け、「予想していない質問だから答えられない……」と焦った経験のある採用担当者もいるのではないでしょうか。
そういった場合、「良い質問ですね。少し考えさせてください」と時間を取ることは全く問題ありません。むしろ、真摯に考える姿勢を見せることで、応募者からの信頼につながります。
採用プロセスに潜むあるある5選とその対策

採用担当者あるあるが発生するのは、面接だけではありません。ここでは、書類選考から内定までの採用プロセスでのよくある事例と対策を紹介します。
(1)同じような経歴・スキルの応募者が多く絞れない
職種や業界によっては、似たような経歴・スキルを持つ応募者が集まりがちです。そのため、差がつきにくく、選考に苦労するケースは少なくありません。
さらに志望動機や自己PRも似たような内容である場合もあります。募集の段階で求める人物像を明確に記載したり、より具体的な志望動機や自己PRを求めたりするといった工夫が効果的です。
(2)選考基準が曖昧で担当者によって評価がバラつく
複数の面接官が関わる場合、評価基準が統一されていないために、同じ応募者に対する評価が大きく分かれることがあります。その結果、選考に時間がかかったり、適した人材を見極められずミスマッチを起こしたりするリスクがあります。
このような事態を防ぐには、事前に明確な評価基準を設定し、面接官の間で共有することが不可欠です。技術力、コミュニケーション能力、チームワークなど、それぞれの項目について具体的な指標を設けると良いでしょう。
(3)応募者から「結果はいつですか?」とひんぱんに連絡がくる
選考結果を待つ応募者の気持ちは理解できますが、ひんぱんな問い合わせは採用担当者の負担になります。
問い合わせを減らすには、選考プロセスと結果通知の時期を明確に伝えることが重要です。「書類選考の結果は応募締め切りから1週間後にお伝えします」といった具合に、具体的な日程を示しておきましょう。
(4)面接の日程が何度も変更になる
面接の日程調整は、採用担当者にとって手間のかかる作業のひとつです。
何度も変更が発生しないようにするには、最初の調整段階で複数の候補日を提示し、応募者にも同様に複数の希望日を挙げてもらうことが効果的です。
また、急な変更の場合は、その理由を教えてもらうことで、相手の状況を理解し、適切な対応を取れます。
(5)内定を出しても次々と辞退される
せっかく内定を出したのに、他社への入社を理由に辞退されるケースも少なくありません。内定辞退が続くと、採用計画がスムーズに進まなくなってしまいます。
内定辞退を防ぐためには、選考プロセス全体を通じて自社の魅力を継続的に伝えることが大切です。面接後のフォローアップや、入社前の懇親会など、候補者との接点を増やす取り組みも効果的です。
採用担当は必見!採用業務を効率化に役立つ4つの対策

採用業務のあるあるを紹介してきましたが、適切な対策をすることで防げる場合もあります。業務を効率化する、おすすめの方法を紹介します。
(1)採用管理システムの導入
多くの応募者の情報を効率的に管理するために、採用管理システムの導入を検討しましょう。
応募者の基本情報・選考の進捗・面接官からの評価コメントなどを一元管理できるため、情報の見落としや重複作業を防げます。
自動メール配信機能を活用すれば、書類選考の結果通知や面接日程の調整も効率化できます。
(2)採用評価シートの標準化
面接官によって評価基準が異なり、採用の質にばらつきができることを防ぐために、標準化された評価シートを作成しましょう。
技術力・コミュニケーション能力・チームワークなど、職種に応じた評価項目を設定し、それぞれ明確な基準を設けることで、客観的に評価できるようになります。各項目に対する具体的な質問例も併記しておくことで、面接官が迷うことなく適切に評価できます。
(3)FAQ集の作成と活用
応募者からよくある質問をまとめたFAQ集を作成し、ホームページに掲載することで、問い合わせ対応の負担を軽減できます。
給与体系・勤務時間・福利厚生・研修制度・選考フロー・結果通知までの期間など、基本的な情報を整理しておくと良いでしょう。FAQ集は定期的に更新し、新しい質問が出てきた場合は適宜追加していくことが重要です。
(4)データ分析による改善
採用活動の効果を測定するために、各選考段階の通過率や採用に要した期間、採用コストデータを収集・分析しましょう。どの媒体からの応募者が最も良い結果を出しているか、どの面接官の評価が最も的確かなど、データに基づいた改善策を検討できます。
入社後の定着率と採用時の評価を照らし合わせることで、選考基準の妥当性も検証できます。
まとめ

採用担当者の日常には、予想外の出来事や共通の課題が数多く存在します。面接でのハプニング、書類選考での悩み、求職者とのコミュニケーションギャップなど、あるあるな体験は決して特別なものではありません。
採用現場のあるあるは、改善のヒントの宝庫です。一つひとつ対策することで、業務効率が大きく向上し、より良い人材との出会いにつながります。





