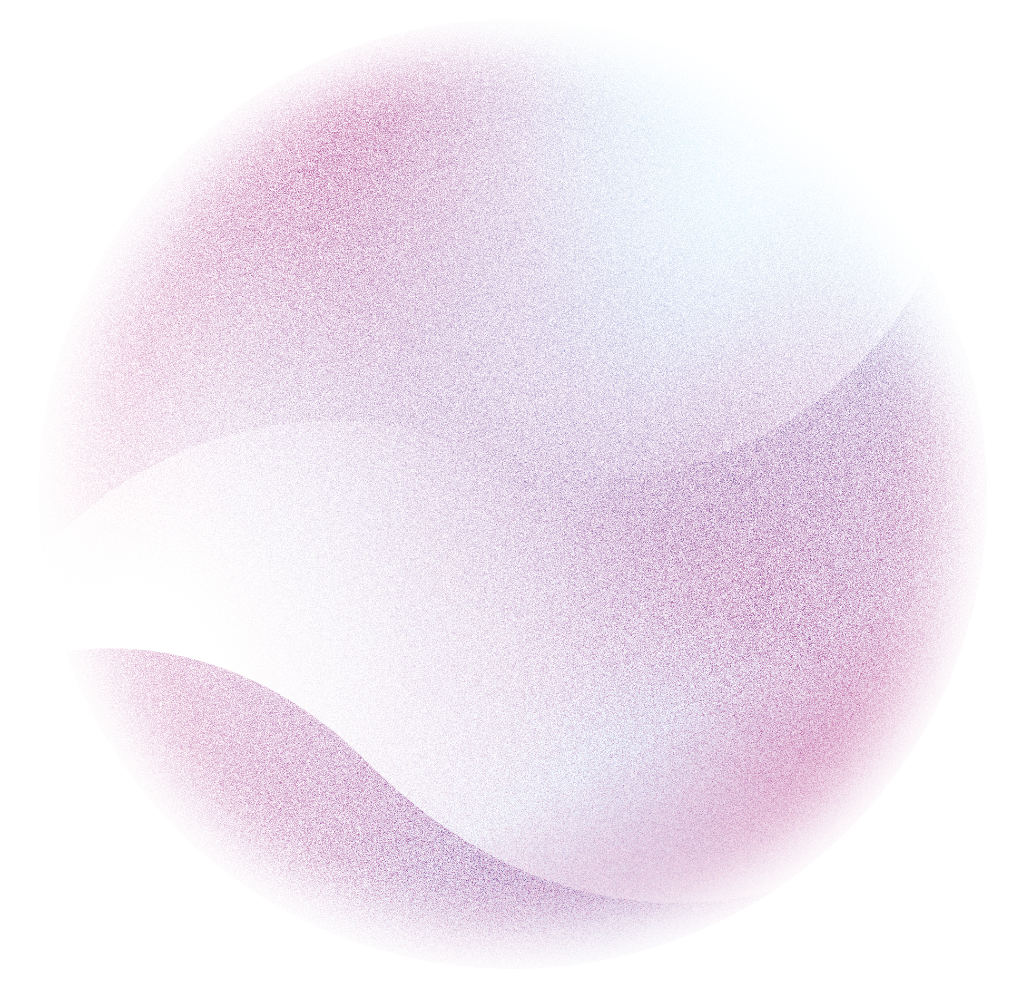
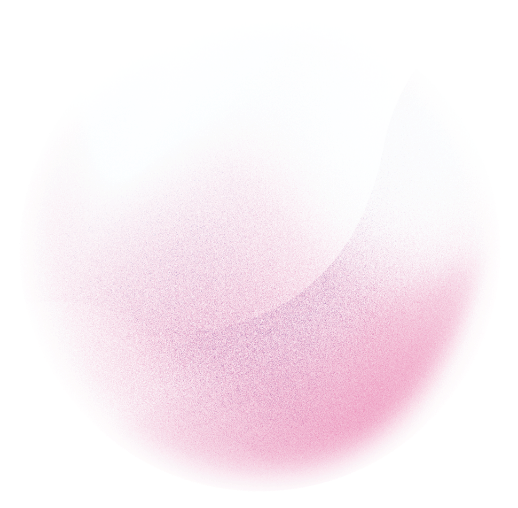
2025.09.11 採用
採用の質を向上させる!面接官トレーニングの重要性と効果的な実施方法

採用活動において、面接は求職者のスキルや人柄、マッチ度を見極める重要なプロセスです。
しかし、面接官のスキルが不足していると、企業の魅力を十分に伝えられなかったり、入社後のミスマッチを引き起こしたりするリスクがあります。
特に、採用のミスマッチは早期離職の原因となり、新たな採用コストの発生にもつながります。
この記事では、面接の効果を高める方法や面接官トレーニングの方法、外部研修を受けるメリットなどを解説します。
質の高い人材を見極める!面接官トレーニングの方法とは

面接の効果を高めるには、以下のような手法を導入すると効果的です。具体的な手法をいくつかご紹介します。
(1)構造化面接を導入する
構造化面接とは、全ての求職者に対して同じ質問項目と評価基準を用いる面接手法です。Google社をはじめ多くの大手企業でも導入されています。
募集職種に求めるスキルや行動特性を明確にし、それらを測るための質問リストや評価シートを作成。事前に決めた手順に沿って、面接を進めます。
例えば、「チームワーク」を評価する場合、「これまでのプロジェクトで意見の対立が起きた際、どのように解決しましたか?」といった具体的な行動を問う質問を用意します。
これにより、面接官の主観や感情に左右されることなく、客観的に候補者を評価できるようになります。
構造化面接を導入することで、面接官間の評価のばらつきを防ぎ、不公平感やミスマッチが発生しにくくなります。
(2)バイアスを減らすための知識を学ぶ
「バイアス」とは、心理的な偏りのことです。誰しもバイアスによって、気づかないうちに自身の主観や感情で求職者を評価してしまうリスクがあります。有名なバイアスを3つ紹介します。
・ハロー効果
特定の優れた点があると、他の部分も優れていると判断してしまう現象です。例えば、有名大学出身の求職者に対し、全ての面が優秀であると思い込むケースが該当します。
・論理的誤差
応募者の学歴・前職の会社のネームバリュー・資格・役職などから関連づけ、求職者の人物像を推測で判断してしまうことです。例えば、大学を中退しているから退職リスクが高いと判断するといった場合を指します。
・寛大化傾向
母校・出身地・趣味などの共通点がある求職者に対し、面接官の評価が全体的に甘くなる傾向を指します。
これらのバイアスは、適切な人材を見逃し、ミスマッチを起こす原因となります。
バイアスの影響を防ぐためには、まず自分自身にどのような偏見があるのかを自覚することが重要です。研修や書籍などで必要な知識を身につけましょう。
複数の視点で評価する、システムを活用するといった対策も効果的です。
(3)ロールプレイングで実践力を磨く
ロールプレイングは、実際の面接状況を想定して行う模擬練習です。一人が面接官役、もう一人が求職者役となって、質問の仕方や受け答え、アイスブレイクの進め方などを練習します。
経験豊富な面接官が求職者役を務めることで、経験の浅い面接官は予期せぬ質問や難しい状況にも対応できるようになります。
練習後にフィードバックを受けることで、自身の課題を認識し、改善につなげられるのもメリットです。
(4)面接マニュアルを作成する
面接の進め方や注意点、採用・評価基準をまとめた面接マニュアルを作成し、トレーニングをしてもらうのも効果的です。
コミュニケーションであれば「人の話をしっかり聞き、理解したうえで答えられるか」といったように、具体的な基準を設けることで、一貫性のある面接を実施できます。
また、新人教育や引継ぎ時の際にも役立ちます。
効果的な面接官トレーニングのために!おさえるべきポイント

面接官トレーニングの際は、以下のようなポイントをおさえることで、着実にレベルアップできます。
(1)採用課題を洗い出す
採用課題によって、必要なアプローチは異なります。面接官トレーニングの前に、自社の採用課題を洗い出し、目的を明確にしておきましょう。
例えば、入社後の早期退職が多い場合は、ミスマッチが発生しているケースが多く、面接官の採用・評価基準の問題が起きている可能性が高いでしょう。そこで面接官トレーニングでは、採用基準の共有と浸透に注力する必要があります。
(2)コンプライアンスやビジネスマナーを見直す
コンプライアンスの遵守やビジネスマナーといった基礎ができていないと、面接官トレーニングをしても、あまり効果が出ない可能性があります。
特にコンプライアンスを守れていない場合、面接官の言動によって自社のイメージが悪くなるだけではなく、名誉棄損などの法的責任が問われかねません。
高圧的に接したり、本籍地や家族など面接に関係のないプライバシーについて質問したりするのは、絶対にやめましょう。
ビジネスマナーについては、清潔感のある身だしなみや丁寧な言葉遣いを意識することが大切です。
(3)実践とフィードバックのサイクルを作る
面接官トレーニングは一度きりで終わらせず、定期的な実践とフィードバックの機会を設けることが重要です。
実践とフィードバックを繰り返すことで、知識・スキルが定着し、面接の質の向上につながります。
(4)効果測定をもとに改善する
面接官トレーニングの目的は、採用活動の効果を向上させることです。定着率の向上などの成果が出ているかを把握するために、効果測定をしっかりし、面接内容を振り返りましょう。
ただし、採用活動の結果が出るまでには時間がかかります。面接辞退の発生率や面接の進行のスムーズさなど、経過部分の効果も測定し、面接官トレーニングの改善に活用しましょう。
外部研修を活用した面接官トレーニングとは?メリットと選び方を解説

自社での研修が難しい場合や、より専門的な知識を習得したい場合は、外部研修の活用が有効です。外部研修のメリットや選び方のポイントを解説します。
(1)外部研修を利用するメリット
外部研修の最大のメリットは、社内にはない専門的なノウハウや最新の採用トレンドを学べることです。例えば、高度な質問スキルや、特定の職種に特化した評価方法など、自社だけでは習得が難しいスキルを効率的に学べます。
また、他社の事例を知ることで、自社の課題を客観的に見つめ直すきっかけにもなります。
(2)外部研修を選ぶ際のポイント
外部研修を選ぶ際は、ただプログラム内容を見るだけでなく、講師の専門性や実績、研修形式が自社のニーズに合っているかを確認することが重要です。
例えば、実践的なロールプレイングを重視するのか、座学で知識を深めたいのかなど、目的に合わせて研修を選びましょう。自社のニーズに合わせて内容を柔軟にカスタマイズできる研修であれば、効率的にスキルアップできます。
その他にも、講師の実務経験の豊富さ、アフターフォローの手厚さなども確認しておきましょう。
まとめ

面接官のトレーニングは、質の高い人材を確保し、企業の成長を加速させるための重要な投資です。適切なトレーニングを通じて、面接官は求職者の本質を見抜く力を養い、入社後のミスマッチを減らせます。
この記事でご紹介した構造化面接やバイアスの知識習得、ロールプレイングなどの手法を取り入れることで、面接官一人ひとりのスキルが向上し、企業全体の採用力が底上げされます。
また、外部研修を導入して、より高度な専門知識・スキルを習得するのも効果的です。
ぜひ、採用活動に面接官トレーニングを積極的に取り入れてみてください。





