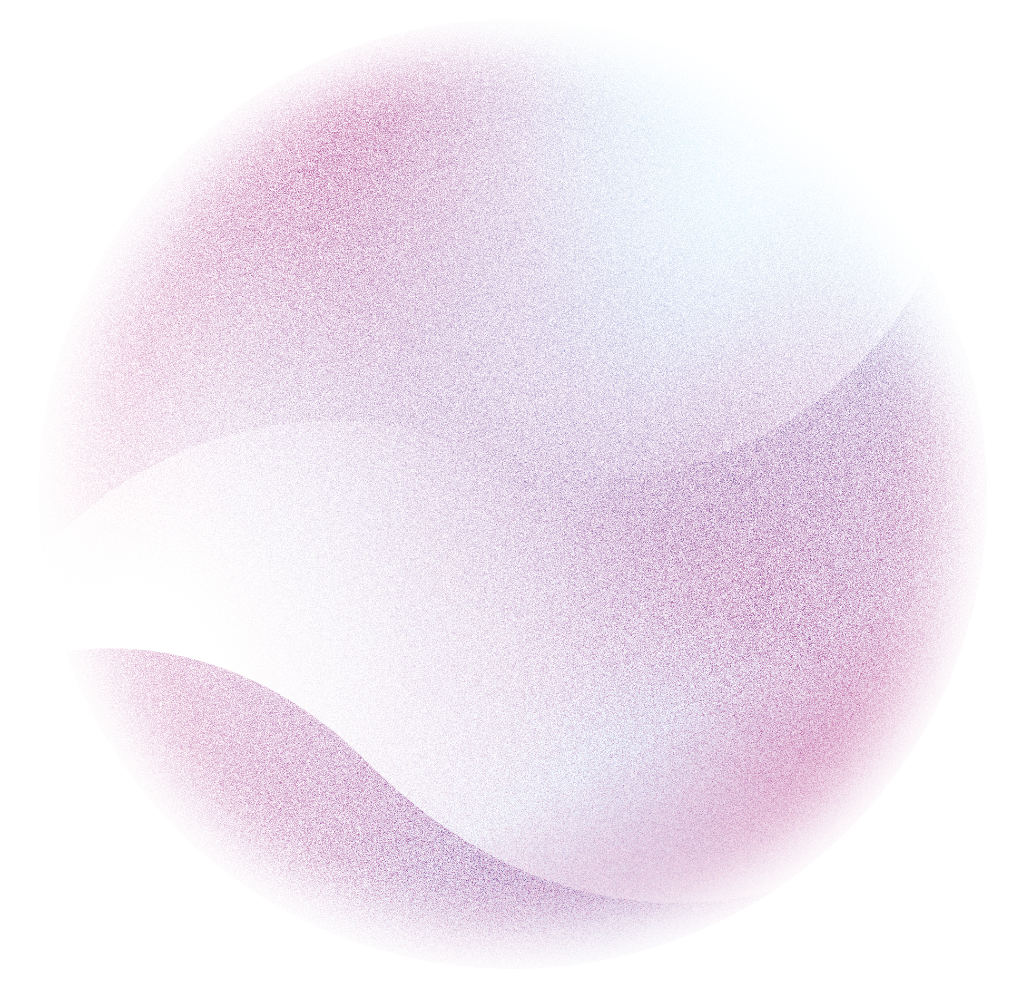
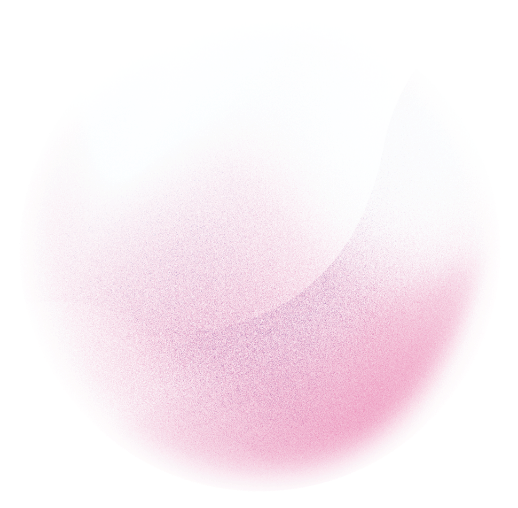
2025.10.17 採用
採用手法にはどんなものがあるの?多様化する採用手法と合わせて解説

売り手市場が続く今、採用手法の選択の重要性はより増しています。加えて、新たな手法の登場や、ツール・AI技術の進化により、採用のあり方は大きく変化しています。
採用を成功させるには、自社に合った手法の見極めが欠かせません。
この記事では、新卒・中途採用における主要な採用手法や新卒採用と中途採用の違い、そして採用手法のトレンドまで詳しく解説します。
新卒採用における主な採用手法とは?代表的な4つを解説

新卒採用では、主に以下のような採用手法が用いられます。
(1)ナビサイト
企業の求人情報を掲載してエントリーを受け付ける、オンラインプラットフォームです。
登録している学生数が多く、広くアプローチできるため、認知度向上と母集団形成を効率的に実施できます。また、企業説明や社員インタビューといった詳しい情報を掲載して自社の魅力をアピールできます。
その一方、同業他社と比較されやすい、数百万円単位で掲載料がかかる場合があるといったデメリットも存在します。
(2)合同説明会
複数の企業が会場に集まり、企業ごとのブースで、学生に向けて自社の採用情報を伝えるイベントです。
1日で数十名から数百名と、短期間で多くの学生と話せるため、効率的に母集団を形成できます。また、学生と対面でやり取りすることで自社の文化や業務がスムーズに伝えられるでしょう。
その反面、多数の企業が参加するため埋もれてしまう、出展料をはじめとするコストや現地で説明する採用担当者の負担が大きいといったデメリットもあります。
(3)インターンシップ
学生に自社で働いてもらい、実際の業務や雰囲気を体験してもらう採用手法です。
相互理解を深め、入社後のミスマッチを防ぐことができる点が最大のメリットです。また、早期から学生との関係性を構築し、志望度を高めることで、優秀な人材を確保しやすくなります。
ただし、企画・運営の工数や担当社員の人的リソースが必要といった負担があります。さらに、参加した学生の満足度が低いと、逆効果になる可能性があるので、入念に計画して実施しましょう。
(4)大学との連携
大学のキャリアセンターと連携し、求人票の掲載や学内イベントへの参加をする方法です。特定の大学・学部・学科に絞ったアプローチができるため、「機械工学を研究している学生を採用したい」といったようにターゲットが明確な場合に特に有効です。
無料または低コストで活用できるケースが多く、採用コストをかけられない中小企業にもおすすめです。
ただし、大学ごとに申請方法や運用ルールが異なり手間がかかる、その大学内の掲示板・システムにしか掲載されず認知拡大が難しいといったデメリットもあります。
中途採用における主な採用手法とは?代表的な3つを解説

中途採用では、主に以下のような採用手法が用いられます。
(1)転職サイト
転職者向けに各企業が求人情報を掲載し、応募を受け付ける手法です。もっとも一般的な採用手法として、多くの企業で導入されています。
転職意欲のある幅広い層に情報を届け、大規模な母集団を形成できる点がメリットです。また、掲載までのスピードが早く、応募を待つスタイルのため、アプローチに関する工数が比較的かかりません。
また、業界特化型の転職サイトを利用することで、特定の層の人材にも効率的にアプローチできます。
ただし、多くの求人に埋もれてしまい応募が集まらないリスクがある、応募者の質がさまざまで選考に工数がかかるといったデメリットもあります。
(2)人材紹介
「転職エージェント」と呼ばれる紹介会社が、登録している求職者から、企業の採用要件にマッチした人材を選び、紹介するサービスです。
自社に合った人材を効率的に見つけられる、成功報酬型なので初期費用をおさえられる、日程調整などを代行してもらえるといったメリットがあります。
ただし、成功報酬が高額である、求職者と直接コミュニケーションが取りにくいなどのデメリットもあります。
(3)ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングサービスのデータベースなどから候補者を探し出し、スカウトメールを送り、直接アプローチする採用手法です。
能動的にアプローチすることで、潜在的な転職希望者や、転職市場に出ていない優秀な人材を採用するチャンスが生まれます。
自社の魅力やビジョンを直接伝えることでミスマッチを防げる点や、長期的な採用コストをおさえられる点もメリットです。
デメリットとして、他の採用手法よりもアプローチに関する工数がかかる、自社の知名度によっては返信率が低くなるといった点があげられます。
新卒採用と中途採用って何が違うの?それぞれの特徴を解説

新卒採用と中途採用の違いを理解することで、より適した採用手法を選びやすくなります。それぞれの特徴を紹介します。
(1)新卒採用の特徴
新卒採用において重要なのは、ポテンシャルと組織への適合性です。学生の基礎能力、成長意欲、そして企業文化との相性を重視して選考します。
スキルや専門知識は入社後の教育で補うため、長期的な視点で、組織の中核を担う人材を育成することに焦点を当てているからです。
そのため、長期的な関係構築につながる採用手法が効果的です。具体的には、就職活動開始前から自社の情報を発信し、時間をかけて魅力を理解してもらう。インターンシップなどを通して早期から自社で働くイメージを持ってもらうといった手法です。
(2)中途採用の特徴
中途採用では、欠員補充や新規事業立ち上げなどの具体的なニーズに応じ、即戦力として活躍できるかを見極めることが重要です。応募職種に必要な専門知識やスキル、過去の職務経験や実績を重視して選考を進めます。
採用手法を選ぶ際は、採用のスピード感と求める人物を確保できるかという点が重要です。転職サイトや人材紹介を活用し、求める経験やスキル、給与などの条件面を明確に示すことが、成功につながります。
アルムナイ採用やAIの活用など採用手法のトレンドを解説

アルムナイ採用やAIの活用といった、注目すべき採用手法について解説します。
(1)アルムナイ採用
アルムナイとは、企業を退職した人材を指します。退職者と良好な関係を維持し、再入社を促す手法が、アルムナイ採用です。
企業文化や業務内容を既に深く理解しており、即戦力として期待でき、入社後の立ち上がりや定着が非常に早いことが最大のメリットです。
退職者向けの交流会や専用のSNSグループなどを設け、継続的にコミュニケーションを取ることで、アルムナイ採用の機会が増えます。
(2)リファラル採用
リファラル採用とは、社員からの紹介や推薦を通じて人材を採用する手法です。
自社の企業文化や仕事内容をよく知る社員が候補者を探すため、ミスマッチが少なく、定着率の向上が期待できます。
一般的な求人広告などに比べて採用コストを抑えられ、潜在的な転職者層にもアプローチできる点が大きなメリットです。
(3)SNS採用
Twitter、Facebook、LinkedInなどのソーシャルメディアを活用して人材を募集・獲得する手法です。企業の日常や文化を継続的に発信し、潜在的な候補者に親近感を持ってもらうことを目的とします。
求人情報だけでなく、自社イベントのレポートなどカジュアルな接点を持つことで、従来の採用媒体ではリーチしにくい層や、転職潜在層へもアプローチできます。
(4)AIを活用した採用手法
採用にAIを活用することで、採用プロセスを効率化し、質を向上できます。
代表的な取り組みが、AIによる書類選考です。履歴書や職務経歴書をAIが分析し、採用基準や過去の採用実績に基づいて、最適な候補者を自動で抽出します。これにより、採用担当者の主観だけではなく、客観的かつスピーディーに選考を進められます。
その他、採用・人材育成・配置・定着・成果まで全てのプロセスを一元管理する仕組みの構築、AIによる面接などの事例があります。
まとめ

売り手市場の継続とデジタル技術の進化により、採用手法は多様化しています。成功の鍵は、自社に最も適したものを選び、戦略的に活用することです。
新卒採用では、ナビサイトやインターンシップを活用し、長期的な関係構築を目指します。一方、中途採用では、人材紹介やダイレクトリクルーティングで即戦力を効率的に確保することが重要です。
アルムナイ採用・リファラル採用・SNS採用といった新しい採用手法を導入する、AIを導入して効率化と質の向上を進めるといった取り組みも進めていきましょう。





